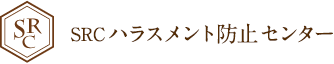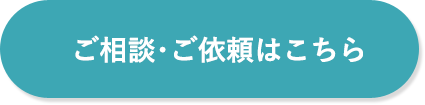全てのステージで会社を守り
社員がいきいき働ける職場作りを、サポートします
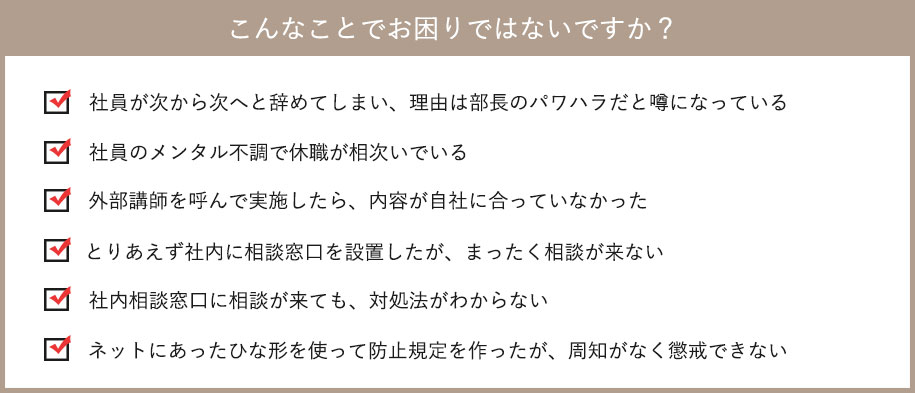

ひとつでもあてはまったら、
まずはSRCハラスメント防止コンサルタントにご相談ください。
目次
- ハラスメントに関する4つの悩みー休職・退職/研修/相談窓口/起こってしまった事案
- ハラスメント事案が起こったとき、こんな対応をしていませんか?
- ハラスメント防止対策、起こってしまった事案への対処は会社の義務です
- 雇用管理上必要な措置とは
- 会社の義務を果たしていないとこんなリスクがあります
- SRCハラスメント防止コンサルタントのプロフィール
- パートナーコンサルタントのプロフィール
- SRCハラスメント防止コンサルタントに依頼する3つのメリット
- SRCハラスメント防止コンサルタントが提供するサービスと標準的な料金
わたしたちSRCハラスメント防止コンサルタントは、
お悩みの解決に向けて、貴社を力強くサポートします。




ハラスメントに関する4つの悩みー休職・退職/研修/相談窓口/起こってしまった事案

増え続ける休職者・退職者の悩み
社員が次から次へと辞めてしまい、理由は営業課長のパワハラだと噂になっている
営業課に配属された社員は、なかなか定着せず、常に募集をかけているのに人手が足りない状況です。
課長の厳しすぎる叱責が原因で、退職者が出ているのだと社内で噂になっています。
営業課長は課長職をしながら営業成績はトップで、彼がやる気を失ったり退職しては困るので、会社も手をこまねいている状態です。
課長がひとりでがんばっていますが、ほかの社員は元気がなく、営業課自体の業績も落ちてきてしまいました。

社員のメンタル不調での休職が相次いでいる
ここ2年ほど「適応障害」や「抑うつ状態」という診断書を持って、休職を願い出る社員が相次いでいます。
いずれ戻ってくることが前提なので、新しい従業員を雇い入れることも難しく、業務の穴を埋めるのに四苦八苦しています。
残った従業員がその影響を受け、残業も増え続けています。
また、休職期間が明けて戻ってきた従業員に対しても、どのように扱ってよいのかわからず、困っています。
休んでいない社員たちからは「休んでも、戻ってきても迷惑ばかりだ。いっそ辞めてくれればいいのに」という声があがっており、職場の雰囲気は最悪です。


ハラスメント防止研修の悩み
社員に講師をやるよう命じたら、資料の棒読みで受講者が寝てしまった
慣れない講師を任された社員は、残業が増えたり、本来の業務にさしつかえが出ていませんか?
しかもうまくいかなかったのでは、「なんで自分がこんなことをやらされるんだ!」という不満を抱えているかもしれません。
また、退屈な研修を聞かされた受講者は、「時間のムダだった」「しょせん社内でお金をかけずにやろうしている。ハラスメント防止なんて口だけだ」と思っているかもしれません。
せっかく研修を実施したのに、会社に不満をもたれる結果になってしまいました。

外部講師を呼んで実施したら、内容が自社に合っていなかった
研修会社に頼んで、ハラスメント防止研修の講師を派遣してもらうのなら安心ですね。
価格は3時間で30万円でしたが、これで効果があるのなら、安いものです。
相手はプロだし、研修もたくさんやっているし、きっといい内容のものだろうと安心して、打合せも簡単にしかしませんでした。
ところが、製造業で工場勤務の従業員がほとんどなのに、研修の内容はホワイトカラーが前提で、「あまり参考にならなかった」という声が多く出て、せっかくの研修もたいした効果もなく終わってしまいました。


ハラスメント相談の悩み
とりあえず社内に相談窓口を設置したが、まったく相談が来ない
会社は、総務部の部長(男性)と、総務部所属の女性社員に、相談窓口担当者の業務を命じました。
しかし、1年たっても相談はゼロ。
社長は「うちにはハラスメントなんてないんだ」と胸を張っています。
しかし総務部所属の社員の間では「しょっちゅうどなっている怖い総務部長のところに、相談なんて来るわけないよね」「入社2年目の若い女性では、相談相手としてちょっと頼りないよね」という話になっています。
そもそも、相談窓口を設置したときに社員に通知したきりで、その後はなにもやっていません。
今月もメンタル不調による休職者が出てしまい、本人が「上司にパワハラされたのが原因」といい出したので、総務部は社長に「相談窓口があるのにどうしていままでわからなかったんだ!」と無茶な叱責をされました。

社内相談窓口に相談が来ても、担当者の対応がどのように対応したらよいかわからない
会社がハラスメント相談窓口を設置してまもなく、上司にパワハラを受けたという相談がありました。
しかし、相談に対応するためのマニュアルもなく、相談担当者はなんの研修も受けていないので、どのように扱ったらよいかわかりません。
担当者が悩んでいる間に、1週間、2週間、1ヶ月と過ぎてしまいました。
メールを出した社員は自己都合で退職してしまい、しばらくして、弁護士から「ハラスメントの被害を受けたので損害賠償を請求します」という内容証明が届きました。


ハラスメント事案の対処がうまくいかない悩み
ネットにあったひな形を使ってとりあえずハラスメント防止規程を作ったが、社員に周知しなかったので、いざというとき懲戒できない
ネットにあったひな形を使い、ハラスメント防止規程を簡単に作成しました。
総務部所属の社員に頼んで労働者代表になってもらい、意見書もつけて労働基準監督署に提出したので、社長も総務部長もこれで安心だと思っています。
その後、会社でハラスメント事案が起こり、ハラスメント行為を行ったことを本人も認めたので、懲戒することにしました。
ところが、懲戒処分の根拠としてハラスメント防止規程の条文を書いた紙を対象者に渡したところ、「こんな条文があったことは知らない」「根拠のない懲戒だから無効だ」と言い出し、もめています。
弁護士に相談したところ、「労働者に周知していない就業規則は無効だから懲戒の根拠にならない」と言われてしまいました。

ひとつでもあてはまったら、
まずはSRCハラスメント防止コンサルタントにご相談ください。
お電話でも受付けております
(社労士法人ハーネス内 受付時間 平日9:00~18:00)
ハラスメント事案が起こったとき、こんな対応をしていませんか?
ハラスメント事案が起こったとき、こんな対応をしていませんか?
セクハラやパワハラの被害を受けているという相談が、被害者の上司や、会社の相談窓口に寄せられたとき、どのような対応をとればよいか、わかっているでしょうか。
「そのときになってから考える」では
遅いことも多いのです





不適切な対応をした結果、
大問題を招いた実例をご紹介しましょう。
実例1
上司がセクハラの相談を受けたが、会社上層部に知らせず内々に収めようとした
2018年、テレ朝の女性記者が、財務事務次官にセクハラを受けていたことを週刊誌で暴露し、大騒ぎになりました。
女性記者はセクハラの録音を持っており、「おっぱい触っていい?」等の露骨なことばがマスコミを賑わせました。
女性記者は週刊誌に情報を持ち込む前に、上司に複数回相談していたにも関わらず、上司は「二次被害の恐れがある」として、公にしていませんでした。
結果、事務次官は辞任し、女性記者の雇用主であるテレビ朝日も、セクハラがあると知りながら放置していた体質を批判されることになりました。

実例2
社内相談窓口にセクハラの相談が来たが、担当者がたいしたことではないと思い、放置していた
2001年、神奈川県内の市職員の女性が、直属の上司からセクハラをされたことを職場内の相談窓口に申告しました。
担当だった課長が半月間放置した後、市はおざなりな調査をして、「セクハラではない」と決定しました。
女性職員が裁判に訴えた結果、セクハラをした上司は120万円、相談を放置した担当課長は80万円の損害賠償を命じられました。
(横浜地裁 平成16年7月8日判決)

実例3
パワハラの被害者が病気休職し、就業規則の自然退職に該当したので、そのまま退職扱いにした
上司に高圧的な叱責を受け続けた結果、適応障害になった社員が、欠勤を続けたところ、会社により業務外傷病の休職規定を適用され、自然退職扱いにされた事案です。
会社はパワハラを認めず、被害者に対して、懲戒にする理由もないのに懲戒解雇をちらつかせ、強く退職勧奨を行いました。
被害を受けた社員が、会社と上司を訴えたところ、裁判所により上司のパワハラが認められた上、退職扱いも否定され、結果として、会社とパワハラをした上司に対して、連帯して419万円の損害賠償を命じる判決が出ました。
(大阪地裁 平成26年7月11日判決)

実例4
パワハラの申告があり調べたら、多くの部下からそれを裏付ける証言があったので、懲戒解雇にした
パワハラの申告に基づいて調査したら、部下10名以上が「行為者の言動に問題があった」と回答したので、就業規則に則り、行為者を懲戒解雇にしました。
その元社員が解雇は無効だと会社を訴え、裁判で行動に問題はあったがパワハラとまではいえず、解雇は無効だという判断が出たので、2年7ヶ月分の給与1,130万円余りの支払いが命じられました。
(高知地裁 令和3年5月21日判決)

実例5
セクハラの相談があり、会社で調べたところ虚偽申告だったので、相談した従業員を懲戒解雇にした
上司にセクハラされたという女子従業員からの申告に対して調査したところ、合意の上で性的関係を結んだのをセクハラと偽っていたとわかりました。会社はこの調査のために大きな労力を使ったので、就業規則に則って懲戒解雇としました。
ところが、その元従業員が裁判に訴え、裁判所が懲戒にする理由はあるが懲戒解雇はいきすぎであり、解雇無効と判断したので、解雇してから裁判の判決が出るまでの3年4ヶ月分の給与740万円と年6%の金利の支払いを命じられました。
(東京地裁 平成26年2月5日判決)

ハラスメント防止対策は会社の義務
ハラスメント防止対策、起こってしまった事案への対処は会社の義務です
法律にはこのように規定されています



セクシュアルハラスメント(セクハラ)
男女雇用機会均等法第11条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(マタハラ)
男女雇用機会均等法第11条の3
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
育児介護休業法第25条
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
パワーハラスメント(パワハラ)
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)第30条の2
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
雇用管理上必要な措置とは
上で見た法律の条文には「雇用管理上必要な措置を講じなければならない」とあります。
「雇用管理上必要な措置」とは、具体的になにをすればいいのでしょうか。
厚生労働省では、「指針(ガイドライン)」を出して、事業主が行うべき措置、行うのが望ましい措置を定めています。

厚⽣労働大臣の指針
- 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇⽤管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告⽰第5号)
- 事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇⽤管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告⽰第615号)
- 事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇⽤管理上講ずべき措置等についての指針(平成28年厚生労働省告⽰第312号)
- 子の養育⼜は家族の介護を⾏い、⼜は⾏うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両⽴が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成21年厚生労働省告⽰第509号)
事業主が行うべき措置(義務)
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。
会社の義務を果たしていないとこんなリスクがあります





法的なリスク
(1)企業(使用者)の法的責任
職場のハラスメントは、被害者と加害者の個人的な問題ではなく、職場全体に深刻な影響を与える組織の問題です。
企業(使用者)には、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法及び育児・介護休業法上において予防を含む雇用管理上の措置が義務付けられていて、企業(使用者)はこれらを遵守して必要な対策をとらなければいけません。
企業(使用者)がこの義務に違反した場合、使用者責任(民法第715条)、労働契約法第5条「安全配慮義務違反」としての債務不履行責任(民法第415条)を負います。
さらにハラスメント防止対策を行っていない企業(使用者)については、不法行為責任(民法第709条、第710条)を負うことがあります。

(2)加害者の法的責任
ハラスメント行為により被害者の人格権を侵害した加害者には、不法行為責任(民法第709条、第710条)が生じます。さらに暴力や脅迫等を伴う場合は、刑法上の「障害」(第204条)、「暴行」(第208条)、「名誉棄損」(第230条)、「侮辱」(第231条)、「脅迫」(第222条)、「強要」(第223条)の罪で訴えるリスクもあります。
また身体接触を伴うセクハラの場合は、「強制わいせつ」(第176条)、「強制性交等」(第177条)等の罪に問われます。
採用リスク
近年、従業員からハラスメントで訴えられるケースが増えています。
訴訟にならなくても「ハラスメントが多い」、「ブラック」等の状況をSNS等で拡散されると、企業イメージが低下してしまいます。そうなると、どんなに多額の費用と時間をかけても採用ができません。
加えて、職場にハラスメント行為が蔓延すると、残った人に負荷がかかり、さらに人材の流出が相次ぐという悪循環に陥るでしょう。
少子高齢化で採用が難しい中、働く側はハラスメントのない「安心安全な職場」を求める傾向がますます強くなってきています。
ハラスメント防止は採用戦略においても重要課題です。

不正・不祥事の温床になるリスク
厚生労働省の「パワハラ実態調査」(令和2年度)では、パワハラが発生しやすい職場の特徴として、パワハラ・セクハラともに「上司と部下とのコミュニケーションが少ない/ない」がトップになっています。また、「失敗が許されない/失敗者への許容度が低い」という項目は2番目にあげられています。
上司と部下とのコミュニケーションが少ないとどういうことが起こるでしょうか?
部下は、わからないことがあっても聞きにくいため、自分勝手に判断して作業を進めた結果、ミスをしてしまったという事例がありました。
また、職場に「失敗が許されない雰囲気」が漂っていたため、無謀な運転で悲惨な事故を起こした例を覚えておられる方も多いでしょう。
さらに、「失敗が許されない/失敗者への許容度が低い」職場で、失敗を隠すためにルールが曲げられると法律違反に発展してしまう危険も潜んでいます。
「現場で悪い情報を報告できない」「困っても相談できない」状況が、会社の存在を揺るがす大きな問題に発展してしまうのです。
パワハラは不正・不祥事の重要な原因になっていることを認識する必要があります。

取引先へのリスク
裁判等でハラスメントを訴えられた企業では、顕在化されていない多くの問題があると考えられます。
取引先は、損害賠償の支払い、人材不足、法違反、不正不祥事の温床となりかねない会社と持続可能な成長を共に続けていけるか不安を感じることでしょう。
また、裁判に発展しない場合でも、SNS等で簡単に情報拡散できるので、良くない評判はすぐに広まり、訂正することが難しくなります。
拡散された情報は、日本だけでなく世界中からチェックされています。日本よりも人権問題に厳しい海外で不買運動につながれば、取引先が離れていくことも想定され、その損失は計り知れません。
グローバル化の進展で「これぐらいは許されるはず」という日本の常識は、通用しなくなっていることを自覚しておきましょう。

労務管理上のリスク
ハラスメントは被害者・加害者だけでなく、周りの従業員が見たり聞いたりするだけでも精神的にダメージを受けてしまいます。その結果、モチベーション低下、休職者や離職者の増加、優秀な人材の流出等により、生産性低下を余儀なくされる場合もあり得ます。
また、メンタル不調には、セクハラ・パワハラの被害を受けることが大きな原因になります。うつ病や適応障害等になると長期休職に結びつきやすく、何度も再発してしまいがちです。最悪の場合は、自殺される可能性もあり、大切な社員を失うだけでなく、遺族から高額の損害賠償(慰謝料)を求められるケースが増えています。
ハラスメントの裁判リスクは、被害者からだけではありません。加害者への事後対応が適切でないと、加害者から「懲戒処分が重すぎる」として、会社を訴える例が後を絶ちません。
ハラスメントに対して防止対策をしっかりとらないと会社の存続危機リスクが高くなるのです。

うちの会社はだいじょうぶかな?
と不安を感じたら、
SRCハラスメント防止コンサルタントにご相談ください。
お電話でも受付けております
(社労士法人ハーネス内 受付時間 平日9:00~18:00)
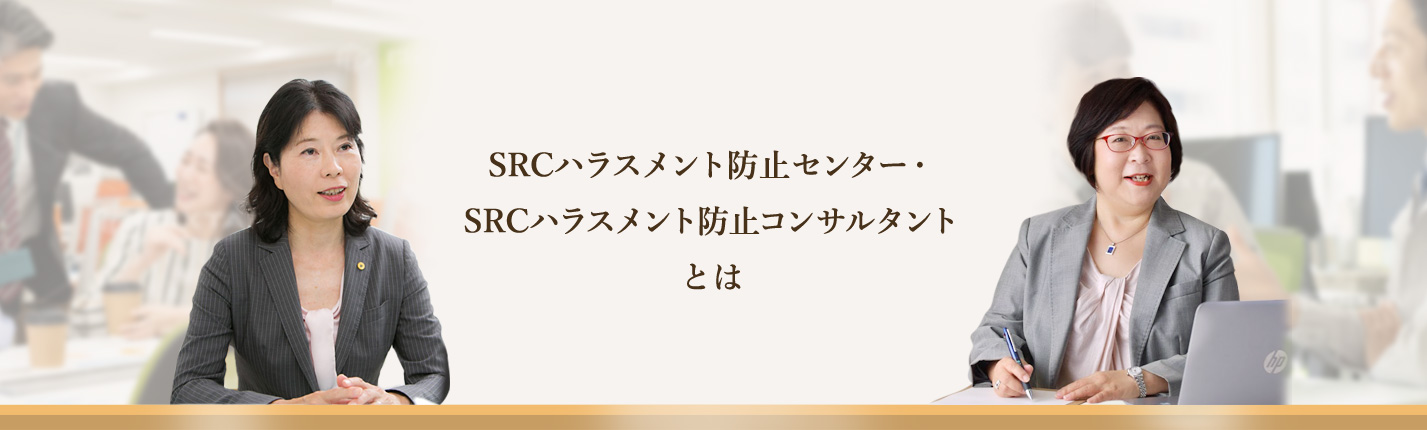
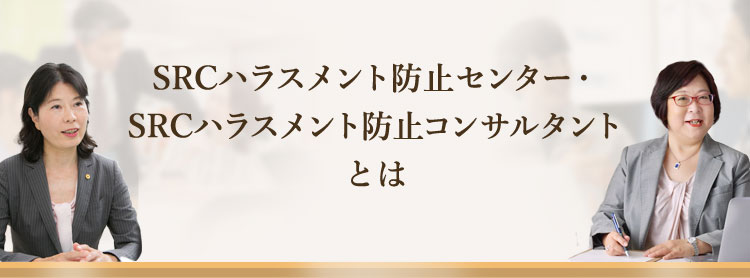
このようなハラスメントをめぐるリスクや悩み事を大幅に軽減するのが、わたしたちSRCハラスメント防止センター・SRCハラスメント防止コンサルタントです。
SRCハラスメント防止コンサルタントは、その場だけの対症療法ではなく、組織全体・被害者・行為者(加害者)すべてがよりよく進化するサポートをしたいという、高い志を持っています。
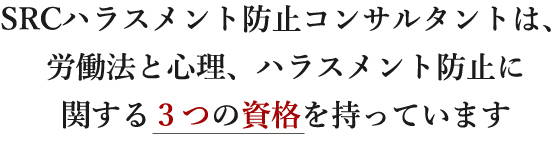

職場の法律の専門家で、厚生労働省が認定する国家資格です。
ハラスメント防止規程(就業規則)の作成・改定や、評価・賃金制度の作成・改定、懲戒処分の相談等の分野で力を発揮します。

産業カウンセラーは、傾聴等の心理学的手法を用いて、働く人たちが抱える問題を、自らの力で解決できるように援助することを主たる業務としています。 相談室でカウンセリングを行うだけではなく、組織自体に働きかける力を持っています。

ハラスメント防止教育や事案解決を行うことのできる専門家です。
企業・団体等におけるハラスメント防止対策の企画立案、意識啓発、教育・研修、相談対応、問題解決の援助等がその活動内容です。
SRCハラスメント防止コンサルタントのプロフィール
研修・コンサルティング等のご依頼は、氏名横の「詳しいプロフィール」から個別のコンサルタントにお問い合わせください。
契約主体は、各コンサルタントとなります。
沼田 博子(詳しいプロフィール)

略歴・資格等
大阪府出身。関西大学大学院商学研究科卒
流通業、人材派遣業を経て社会保険労務士として開業
1996年 社会保険労務士事務所 開業
2001年 有限会社マンパワーマネジメントシステムズ設立 取締役就任
2016年~2020年 関西大学会計専門職大学院 非常勤講師
2017年 社会保険労務士法人ハーネスに組織改編 代表就任
李 怜香(詳しいプロフィール)

略歴・資格等
岐阜県生まれ。早稲田大学卒業。
1999年 社会保険労務士登録し、李社会保険労務士事務所(現 メンタルサポートろうむ)開業。
2011年 産業カウンセラー登録。
2012年 ハラスメント防止コンサルタント認定。公益財団法人21世紀職業財団ハラスメント防止客員講師に就任。
2013年~2019年 厚生労働省委託事業 パワハラ対策取組支援セミナーに登壇。
2016年~2017年 厚生労働省委託事業にて女性活躍推進アドバイザーとして活動。
2019年 健康経営エキスパートアドバイザー認定。
パートナーコンサルタントのプロフィール
パートナーコンサルタントは、社会保険労務士及び、ハラスメント防止コンサルタント、もしくは産業カウンセラー等の心理系資格を持ち、ハラスメント対策に対応できるコンサルタントです。
希望者のみプロフィールを公開しています。
研修・コンサルティング等のご依頼は、氏名横の「詳しいプロフィール」から個別のコンサルタントにお問い合わせください。
契約主体は、各コンサルタントとなります。
押野 りか(詳しいプロフィール)
-257x300.png)
略歴
岡山県生まれ。
広島大学附属福山高等学校卒業。
岡山大学文学部卒業。
2010年 社会保険労務士登録、押野労務サポートオフィス開業。
2012年~2014年 倉敷労働基準監督署 非常勤職員として勤務。
上野 雅子(詳しいプロフィール)

略歴
山口県宇部市出身、東京都在住。
2022年 新宿区semina社会保険労務士事務所開業。
同年 産業カウンセラー登録。健康経営エキスパートアドバイザー認定。
2023年 ハラスメント防止コンサルタント認定。
2024年 シェルパ社会保険労務士法人代表社員。
五百川 篤子(詳しいプロフィール)

略歴・資格等
山口県生まれ。山口大学人文学部卒業。
2015年 社会保険労務士登録
2017年 いおがわ社会保険労務士事務所開業
2018年 キャリアコンサルタント登録
2019年 特定社会保険労務士の付記
2020年 労働者健康安全機構 治療と仕事の両立支援コーディネーター
2021年~厚生労働省委託事業にて女性活躍推進アドバイザー
2023年 ハラスメント防止コンサルタント(公益財団法人 21世紀職業財団)
谷口陽子(詳しいプロフィール)

略歴・資格等
岐阜県出身。
大手製造業の人事総務を経て、2015年社会保険労務士登録
現在 社労士オフィスソレイユ 代表
2017年 国家資格キャリアコンサルタント資格取得
2019年 公益財団法人 21世紀職業財団認定ハラスメント防止コンサルタント
同年 アンガーマネジメント協会認定ファシリテーター
2022年 アンガーマネジメント協会認定ハラスメント防止アドバイザー
2019年~ 厚生労働省委託事業にて女性活躍推進アドバイザー
SRCハラスメント防止コンサルタントに
依頼する3つのメリット



SRCハラスメント防止コンサルタントに依頼する3つのメリット
1.総合的なコンサルティングにより、ハラスメントを元から断つことができる
ハラスメントの問題を、被害者と加害者間の個人的な性格によるものとすることは、根本的原因に対処することができません。
ハラスメント問題が発生している状況は、ハインリッヒの法則(氷山モデル)で例えると顕在化されている部分は1割で、見えていないが潜在化している問題が9割あると考えるべきです。
見えていない水面下の部分には、職場環境、風土、労働条件、コンプライアンス、技術、評価等の根本的原因が隠れています。ハラスメントを防止するためには、根本的原因に対処していく必要があるのです。
私たちは、社労士として、労働諸法令及びハラスメントの裁判例に精通しています。コミュニケーション研修だけでなく、長時間労働等の見直し、評価制度等への改善をご提案できます。また、産業カウンセラーとして、パワハラ防止指針にある「相談者の心身の状況や言動が行われた際の受け止めなどその認識への配慮」をしながら、その発生の防止、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合などへの相談も広く対応し、適切な対応をする能力があります。
2.豊富な経験、最新の知識、そしてカウンセリング力をもった専門家にいつでも相談できる
職場では、パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ等様々な「いじめ・いやがらせ」があります。私たちは、多くの種類のハラスメントへの対処だけでなく、若年者・女性・シニア・外国人等の多様な価値観を持つ人材が働く職場での事案にも対処してきました。
また、ハラスメントが複合している例や、パワハラの6類型には当てはまらないけれど、退職者が続出して職場が崩壊してしまった例等への対処経験もあります。
これらの中には、傷害で刑事事件に発展した例やあっせんや裁判となった例も含まれています。
職場のハラスメントは、個人間の問題ではなく、組織として対応すべき重要な問題です。
法律の知識と心の知識があり、多くの事案の対処経験のある専門家に早く相談し、しっかり対処していきましょう。
3.適正な価格設定で、継続的なハラスメント対応ができる
ハラスメント対策に費用がかかりすぎると、ハラスメント防止規程を策定して終わり、ハラスメント防止研修を1回だけ行って終わり、ということになってしまいます。
高い費用を払ったのだから、しばらくはこれでいいだろう、という気持ちになるのも無理はありませんが、ハラスメント防止対策は、継続的に行うことが大切です。
そのためには、数年にわたって続けられるような価格設定であることが必要です。
わたしたち SRCハラスメント防止センターでは、中小企業でも無理なく取り組める価格設定で、継続的なハラスメント防止対策をサポートします。
SRCハラスメント防止コンサルタントが
提供するサービスと標準的な料金
記載の料金はすべて別途消費税を申し受けます。
ハラスメント対応総合コンサルティングパック
1ヶ月50,000円~(1年契約)
企業規模に応じてお見積りいたします。
コンサルティング
表面に出ているハラスメントの原因は、長時間労働、コミュニケーション不足、評価制度の機能不全、管理職の指導力不足等、会社によって様々です。
経営者・従業員ヒアリング・アンケート・チェックリスト等の方法でその根本原因を探り、適切な対策を提案するコンサルティングを行います。
ハラスメント対策を超えて、会社の体質自体を強化することができます。
ハラスメント防止・社内コミュニケーション等のご相談
ご訪問/オンラインでのコンサルティングに加え、日頃の社内のハラスメントやコミュニケーションについてのご相談を随時お受けします。
ハラスメント外部相談窓口
さらに、ハラスメント外部相談窓口サービスが付加されます。
相談対応に経験豊富なSRCハラスメント防止コンサルタントが担当しますので、安心してご相談いただけます。
オプションサービス
上記コンサルティングの結果、貴社に最適な方法をご提案し、実行をサポートします。
総合コンサルティングパックご利用中のお客様は、下記の標準的な料金から 20% オフとなります。
各サービスは、コンサルティングとは別に、単発のご利用も承ります。
ハラスメント防止規程/就業規則の整備
100,000円~(別途お見積)
ハラスメント防止研修
3時間 200,000円~(時間・受講人数・内容により別途お見積)
完全なオーダーメイド研修です。
管理職向け・一般向け等階層別研修、相談窓口担当者研修、各種コミュニケーション研修等、貴社の実情に合わせて柔軟に対応します。
各種人事労務コンサルティング
別途お見積
・長時間労働削減対策
・コミュニケーション促進対策
・評価制度の見直し
・管理職の指導力強化
ハラスメント外部相談窓口
1ヶ月15,000円~(1年契約)
ハラスメント事案のヒアリング調査
ハラスメント事案が発生し、下記の方たちにヒアリング調査が必要な場合代行します。
・行為者(加害者)
・被害者
・同僚等の関係者
打合せ+2時間までのヒアリング:
すでに定期的な契約があるお客様 1回 20,000円
上記以外のスポット契約のお客様 1回 50,000円
ヒアリング回数が2回以上の場合は別途お見積り
報告書:
ヒアリングで判明した事実関係、関係者の心理状態について報告するとともに、懲戒方針等、今後の対応についてのアドバイスをいたします。
すでに定期的な契約があるお客様 1回のヒアリングにつき 50,000円
上記以外のスポット契約のお客様 1回のヒアリングにつき 100,000円
ヒアリング回数が2回以上の場合は別途お見積り
面談して報告する場合、5,000円/30分(スポット 9,000円)
対面の場合は交通費別途
ハラスメント被害者のカウンセリング
3回35,000円(それ以外の場合は別途お見積)
再発防止プログラム
100,000円~(別途お見積)
・行為者面談
・組織開発
安全衛生委員会、懲戒委員会参席
1時間 20,000円
懲戒委員会意見書提出:40,000円~